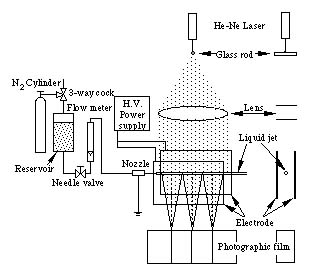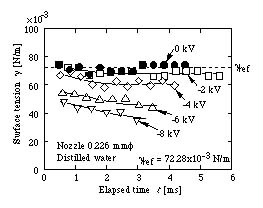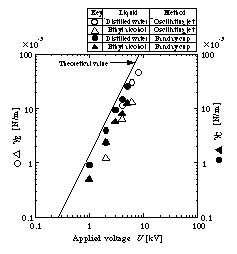概要
液体の表面張力は物性値として決まっているが、電界を印加することによって変化することを、筆者らが以前報告した[1]。被測定液体に接触せずに電界印加のできる唯一の方法として、振動液柱法を用いた。表面張力低下量は、印加電界強度の2乗に比例して増加した。ここでは、流出液体の表面電荷密度を求め、計算した表面張力低下量と理論低下量との比較を行った[2]。
実験
実験装置の概略を図1に示した。試料液体はガスの圧力によって押し出され、ニードルバルブで流量を調整され、ノズルより液柱として流出する。He-Neガスレーザからのレーザ光はガラス棒で分散されてから、レンズで集光され、二次元平行光線となって液柱を照射する。液柱の波によって屈折したレーザ光はカメラ内のフィルムに直接像を結ぶ。フィルムを現像後、スキャナーで読みとり、パソコン処理によって波長を求めた。表面張力算出には、筆者が提案した式[1]を用いた。
直流高電圧は、液柱を挟む一対の平板電極とノズルとの間に印加される。ノズルは注射針を加工したもので、平均内径が0.226
mmと0.304 mmである。液柱を強制的に振動させるために、ノズル出口は楕円形状にしてある。電荷量測定の際には、ジェットを垂直に配置し、ファラデーケージとエレクトロメータによって測定した。試料液体として、蒸留水、電解質水溶液、エタノール、ヘキサン、界面活性剤溶液を用いた。
実験結果
図2に、蒸留水の測定結果を示す。電圧が上昇するにつれて、表面張力の値が下がっていることがわかる。エタノールについても低下がみられるが、導電率の極めて小さいヘキサンの場合には、全く変化がなかった。
蒸留水に電解質を加えて導電率を上げると、表面張力の低下量も増加した。
図2 電界による蒸留水の表面張力変化
図3に示したのは、振動液柱法で測定した表面張力低下量(γE)と、測定した表面電荷量から計算した低下量(γC)の比較である。両者はよい一致を示し、理論線にも近い値であることがわかる。
図3 表面張力低下量の測定値と理論値との比較
文献
1) 佐藤正之, 鬼頭正和, 佐賀井武: 化学工学論文集, 3(5), 504 (1977).
2) Sato, M., Kudo, N., and Saito, M., Conf. Rec. -IAS Annu. Meet. (IEEE),
pp. 1762 (1996).
3) Sato,
M., Kudo, N., and Saito, M., IEEE Trans. Ind. Appl., 34(2), 294 - 300 (1998).